第九話:且固命也?元朔五年(BC124年)、石奮が高齢で死に息子の石建も一年余りで亡くなった。 石建が死ぬと郎中令が空席となったので、武帝は李広を呼び戻して郎中令に任じた。 (郎中令は九卿の一つで、宮中の兵を掌っていた。) しかし、六年に入ると再び匈奴討伐に駆りだされ、大将軍衛青に従い定襄郡から出撃した。 この時、衛青・霍去病が対匈奴戦で頭角を現しており、李広はその下についていた。 勝ち戦であり、功績を取り上げられ列侯となったものが多かったが、 李広には軍功がなかった為、列侯にはなれなかった。 三年後の元狩二年(BC121年)、匈奴が度々侵入し、 李広は郎中令のまま四千騎を率いて右北平郡から出撃、 衛尉の博望侯張騫は一万騎を率いて別道で出撃した。 数百里進軍したところで、李広の軍は匈奴の主力である左賢王率いる四万騎に 包囲されてしまった。 張騫の軍は期日に遅れて到着しておらず、李広軍は絶体絶命となった。 李広は皆を落ち着かせる為、敵の出方を見ると称して息子の敢に命じて匈奴軍に突入させた。 李敢は数十騎で匈奴軍に突っ込んだが、匈奴兵は逃げ散って道を開け李敢は生還した。 李敢は「胡などくみしやすいものです。」といい、兵たちはどっと湧いた。 そこで李広は円陣を組み外に向かって構えたが、左賢王軍は一斉に殺到し 矢を雨のように降らせた。 李広軍は半数が死に、自軍の矢も尽きようとした。 李広は兵たちに、必中するまでは矢を引き絞ったままにせよと命じ、 自身は大弓を引き、左賢王軍の副将を射殺し、続けて数人を射殺した。 左賢王軍は指揮官数名を失いひるんだ。 この時、ちょうど日が暮れ戦闘が止んだ。 兵たちは絶望的な状況を改めて知り、全員が恐怖で青ざめ生気を失った。 李広だけは普段と同じ振る舞いであり、部下を督励し陣を整えさせた。 軍は生色を取り戻した。 翌朝、再び戦闘が始まりほとんどの兵が戦死したが、ようやく張騫の軍が到着。 挟撃を恐れた左賢王は包囲を解き、去った。 李広・張騫は追撃できるわけもなく、漢土へ帰還した。 李広軍は左賢王軍の三千人以上を殺したが、自軍はほぼ全滅、四千人を失った。 張騫は期日を守らず李広を死地に置いた罪で死罪となった。 張騫は罪を金で贖い、庶民となった。 李広は功罪が同じであるとして、恩賞が無かった。 従弟の李蔡は文帝の時代に李広と共に郎となったが、次第に昇進し 景帝の時代には二千石の官職に就き、武帝の時代には代国の相となった。 元朔五年には軽車将軍として衛青に従い、匈奴右賢王を攻撃して勝利し、 恩賞の規定にも合っており楽安侯に封じられた。 張騫の遅延で漢軍が大敗した元狩二年(BC121年)、李蔡は遂に丞相に任じられた。 位人身を極めたのだ。 ただ、李蔡の評判はあまり良いものではなく、当時「下の中」くらいの人柄と称され、 名声は李広のはるか下であった。 しかしながら李広は爵位も封土も得られず、官は郎中令の九卿止まりであった。 李広の部下の中には侯に封じられた者もいた。 李広は占い師の王朔と話をしている時に、自分の運命を嘆いた。 「わしは対匈奴戦争が始まってから、ほぼ全て戦闘に参加してきた。 しかし、兵卒程度の者で、才能が常人以下の人間が軍功で封侯を受けている。 わしは人に遅れを取ったことは一度もないが、わずかの功績も認められず、 領地を受けることもなかった・・・。なぜなのか。 王先生はわしの人相を見て、列侯になれる人相でないと思われるか。」 王朔は、「将軍は過去を振り返って、後悔する出来事がなかったでしょうか。」と言った。 李広は、「わしが隴西郡の太守だった頃(景帝の頃か)、羌族が背いたが、 わしは誘って八百人を降伏させた。だがこの八百人を騙して皆殺しにした。 今まで後悔しているのは、ただこの一事だけだ・・・。」 王朔は、「すでに降伏した者を殺すことより酷いことはありません。 これこそ将軍が列侯になれなかった原因です。」と言った。 李広は辺境七郡の太守を歴任し四十年に及び、賞を得ればすぐ部下に分け与え、 飲食は兵達と共にし、家には財産が無く、生涯生活のことは口にしなかった。 背が高く、特別腕が長く射術に長じていた。 子供らや部下がいくら李広に習っても、かなう者はいなかった。 軍陣にあっては無口で、いつも地面に陣を描いて軍議をし、的を用いた射撃を生涯楽しんだ。 砂漠の中で食料が欠乏し、オアシスを見つけても兵が皆飲んでからでなければ水に近づかず、 皆が食べてからでなければ食料に手をつけなかった。 兵卒は皆、李広に心服し喜んで命に従った。 李広は、敵が数十歩以内に近づかなければ矢を放たず、放てば必ず敵を倒した。 世間では、だから敵に苦しめられしばしば傷つけられたのだと噂した。 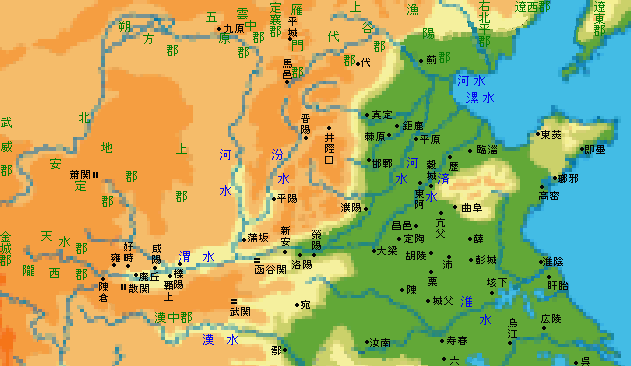 |
HOME 第十話