後漢書列伝第七十四巻 董祀妻伝より 時は、後漢末期。 朝廷では董卓が政治を牛耳り、漢の命脈は尽きようとしていました。 三国志演義でも、曹操の若かりし頃のこととして董卓暴虐のことが書かれています。 董卓はとても野蛮な人なのですが、不思議なことにある有名な大学者を優遇しています。 その有名な学者とは、文人で琴の名手だった名士蔡 董卓はなぜか彼を大変気に入り、次々と出世させて左中郎将にし、その才能を高く評価しました。 しかし、今回のお話しは、そういった男臭いお話しではありません。 蔡 蔡 その上、父から直伝の琴の技量は素晴らしく、人々は音楽の天才と彼女を褒め称えました。 彼女は妙齢となり、衛仲道という男性に嫁ぎますが、すぐに死に別れてしまいます。 悲しみ、途方に暮れた蔡 実家に帰った蔡 父の蔡 父は遺言で、蔡 蔡 彼女は頼るべき者を次々と失い、涙に暮れる日が続きました。 しかし、天が彼女に与えた運命はさらに過酷極まるものでした。 この頃、中国は大乱に陥り、南匈奴(北方異民族)の兵が中原を荒しまわっていました。 頼るべき者もない蔡 匈奴兵は、高貴な若い女性を捕えたことを匈奴王に報告しました。 すると南匈奴王於夫羅(おふら)は、蔡 蔡 父から託された古書四千巻もすべて失ってしまいました。 劉豹とは言葉も通じず、夫の性的欲求を満たすだけの存在に墜ち、父の遺言に背き、 彼女は悲嘆に暮れる日々が続きました。 しかし、そんな悲しみの中でも、喜びごとがありました。 蔡 そして彼女は、二人も劉豹の子どもを生んだのです。 子どもを産んでからは、劉豹にも愛されるようになりました。 蔡 しかし、現実は残酷でした。 曹操が中国で覇権を握ると、彼は北方に連れ去られた蔡 曹操は匈奴王に黄金宝玉を山ほど贈り、蔡 蔡 彼女は慟哭し、悲しみは尽きませんでした。 しかし、命令は絶対・・・。 二人の子どもは去ってゆく母の馬車を追いかけて転んでは起き転んでは起き、 体も顔も泥んこになりながら母の名前を泣き叫び続けました。 蔡 その後、曹操の命令で董祀という男性と再婚させられます。 董祀は慈しみ深く彼女をいたわったので、蔡 が、夫の董祀はつまらぬことで法を犯してしまい、死刑を宣告されてしまいました。 もう二度と離別の悲しみを味わいたくない蔡 素足で曹操の自宅へ駆け込みました。 ちょうどその時、曹操の賓客が大勢集まり、座敷にはびっしり人が詰めていました。 しかし夫の助命だけを念じている蔡 彼女は髪を振り乱し、頭を地べたにすりつけて夫の罪を詫びました。 その話しぶりはとても悲痛で、一座の者はみな粛然としました。 法を厳守してきた曹操もこのときだけは情を動かされ、董祀の死刑を取り消しました。 その後、曹操の命令で、父から託された四千巻の古書を文章化するように命じられ、 暗記していた四百篇だけを書き上げたそうです。 一字も誤字脱字がなく、曹操は大いに驚いたといいます。 蔡 蔡 最後に、 乱世で流浪した自分の痛ましい記憶から、彼女が悲憤のあまり作った詩が二つ残っています。 そのうちの一つの原文・口語訳を挙げて、この伝を終りにしたいと思います。 |
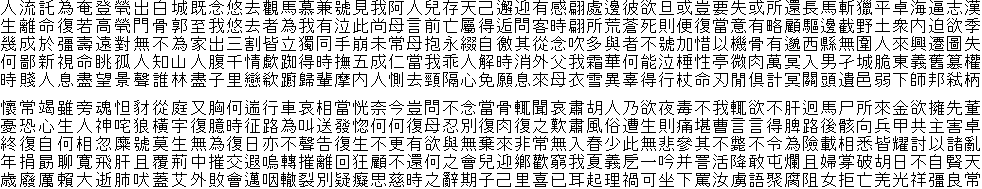
後漢末期、劉氏は権力を失い、董卓が天下を滅茶苦茶にした。
彼は帝を殺して天下を奪おうと考え、手始めにに多くの賢臣良臣を殺した。
董卓は経済的に行き詰まり、長安に遷都を強行し、自分が立てた献帝を後ろ盾として権力を手中に収めた。
天下の諸侯は同盟し、義兵を興して董卓を討とうとした。
董卓の援軍は東の洛陽に向かい、刀槍や鎧は日の光で輝いていた。
中原の人は戦争に弱いが、董卓の援軍はみな戦争に強い蛮族(匈奴)であった。
野戦や攻城戦では、中原の兵はことごとく敗北した。
中原の兵は首を斬られて一人として生き残る者はなく、おびただしい死骸はお互いを支え合うほどに折り重なった。
匈奴兵は、自分の馬の側面には斬獲した中国兵の首をかけて功を誇り、馬の後ろには略奪した女性を乗せた。
捕虜となった大勢の女性たちは匈奴の本拠地に連れ去られたが、とても長い道程でその上険阻な路であった。
今きた道を振り返って見ると、中原は遥か遠くになってもう見えず、心はボロボロになり悲しみは尽きなかった。
匈奴兵が略奪した女性は数万人であったが、捕虜の女性たちを一箇所には集めずに、しかも休止無しで行軍を続けた。
あるいは、母と娘、姉妹そろって略奪された者もあったが、お互いにものを言おうとしても語らせてもらえない。
行軍中、少しでも匈奴兵の機嫌を損ねると必ず、「このくたばり損ねの捕虜め!」と決まり文句で罵られる。
殺されたくないばかりに辛抱していれば、「俺たちはお前を生かしてはおかぬぞ!」と脅迫する。
こんな罵詈雑言を言われ続け、どうして命を惜しむのか!!命なんか棄てたかった。
また、ムチや棒で叩きのめされ、恨み・苦しみ・痛みを味わいながら歩いた者もあった。
夜明けには号泣して歩き、夜更けには悲しみに堪えかねてうめき泣いた。
自殺しようとしたができず、生きのびようと思っても何一つとして良い事がなかった。
天よ、私たちに何の罪があって私をこんな目に遭わせるのか・・・。
遠い辺境の匈奴の人々は、人が踏み行うべき道を知らない。
私がいた所は、冬には霜や雪が降り、春と夏には北方の砂漠から強い風が吹いてくる。
風は私の衣服をばたばたと揺らせ、ひゅーひゅーと私の耳に入ってくる。
私を育ててくれた両親のことを思い出す時は、喜びの記憶と悲しみの気持ちが止むことなく思い起こされる。
中国から客が来たと聞くと、いつも私は喜んだ。
その客を迎え入れて中国の事情を聞くと、故郷はいつか変わってしまい昔の姿はないと言う。
しかし、偶然がこの私の願いをかなえてくれ、一族の者が私を迎えにきてくれた。
すでに私は囚われの身から自由の身となったが、愛するわが子と別れなければいけない。
血のつながりというものは人の心をつなぐもの、ここで愛する子どもたちと別れたらもう二度と会うことはないと思った。
残されるわが子たちと、いなくなってしまう母である私、もう永遠に会えないであろうと思い、去るに忍びない。
子どもは私の首を抱き言う。「ねえ、お母さんはどこにいっちゃうの?
みんなはね、『あなたのお母さんは行ってしまうんだよ。もう帰ってこないんだ。』と言ってるよ。
いつもお母さんは優しく愛してくれたのに、何で今は優しくしてくれないの?
ボクはまだ子供なのに、これから誰に看てもらえばいいの?」と。
これを聞いて私の心はひきちぎれ、何も考えられずぼんやりし心は狂い乱れた。
号泣して泣き叫びながらわが子の手を撫でたりさすったりしていたが、出発が近づいてくると心は別れに惑うばかりであった。
あわせて私と同じくして捕虜となった女性たちが、みな見送りに来て別れの言葉をかけてくれた。
私が一人で中国に帰るのを羨ましがり、別れに悲しんで声は割れて裂けんばかりであった。
その悲しみの声で馬は驚いて立ち上がり、車輪は回らず前に進まなかった。
見物にきた者はみなすすり泣き、道を往き来する人もみな泣いた。
涙を振り絞り、去って去って子どもを慕う情を断ち切り、馬車を急がせて遠ざかった。
はるかに三千里離れたが、いつかまた会えるのだろうか?
私の腹から産まれた子どもたちを思うと、胸の内は崩れ去ってばらばらになる・・・。
実家に到着してみると戦乱で家人は一人もいなくなっており、また身内も隣人もいなくなっていた。
私の故郷の街は木が生い茂り山林となり、実家の庭はヨモギで覆い尽くされ、壁には茨が張り付いている。
転がっている白骨は誰なのか名前も判らず、散乱していて覆うべくものも無い。
家の門を出てみても人の声はせず、ただ狼や犬の遠吠えが聞こえるだけである。
私は一人ぼっちで、孤独な影がただ地面に映り、嘆き嘆いて心はすり減ってしまった。
高い所に登って遠くを眺めて見れば、思いは遠く離れたわが子たちのもとへ飛んでいく。
息も絶え絶えになり死んでしまうほどであったが、側にいる夫が慈悲深くいたわってくれる。
私は夫の優しい気持ちで息を吹き返すが、たとえ生きたとしても何を頼っていけばよいのだろう?
今、私は命を新しい夫に託して、心を尽くして謙虚に仕えよう。
流浪して賤しい身となり、また見捨てられてしまうのではないかといつも恐れている。
人の生にはどれほどの時間があるのだろうか、悲しみ嘆いて一生を終えるのだろうか・・・。
私、おばらの意訳・超訳です。
激しい誤訳があるかもしれませんが、ど素人なのでどうか目をつぶってくださいね^-^;;
戻る